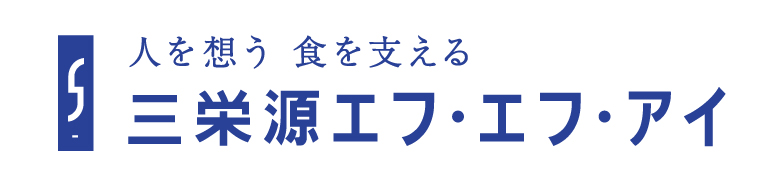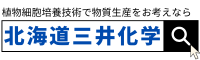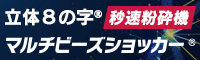- HOME

- シンポジウム
シンポジウム
S1「一細胞からフィールドで捉える植物二次代謝物の新機能」
Advances in the Functional Analysis of Plant Specialized Metabolites: From Single-Cell to Field Scale
オーガナイザー:杉山龍介(千葉大学)、棟方涼介(京都大学)
概要:植物が生み出す多様な二次代謝物は、成長制御や他生物とのコミュニケーションなどに利用される。また、植物由来の揮発性分子(Biogenic Volatile Organic Compounds, BVOCs)はその大気中の量や反応性の高さから、気候にまで影響を及ぼす。しかし、自然環境における植物分子の役割は多くが未解明である。本シンポジウムでは、植物二次代謝物の新機能を明らかにする取り組みとその成果の一端について紹介する。一細胞解析や、フィールドでのリアルタイム質量分析など、ミクロ~マクロスケールの最新技術を二次代謝研究にどう生かすか、討論を行う。
瀬戸義哉(明治大学)「根寄生植物が生産するフェニルエタノイド配糖体の生物学的意義」
相原悠介(神戸大学)「植物二次代謝物の細胞内標的タンパク質を同定するためのプロテオミクス解析」
白川一(IPMB, Academia Sinica)「一細胞レベルでの解析技術を用いた植物二次代謝研究」
棟方涼介(京都大学)「BVOCの気候フィードバック:ブナ科におけるイソプレン合成酵素の分子進化」
大西利幸(静岡大学)「BVOCが強化する植物の環境ストレス耐性の分子メカニズム」
関本奏子(横浜市立大学)「生態系内におけるBVOCの時空間イメージング」
S2「AIが拓く植物バイオの新時代」
The New Frontier of Plant Biotechnology Unlocked by Artificial Intelligence
オーガナイザー:福島敦史(京都府立大学)、庄司 翼(富山大学)
概要:AI技術の進化が、植物バイオ研究の新たな可能性を切り拓いています。生成AIによる知的生産の革新、機械学習を活用した画像解析、文献データからの知識抽出など、最先端のAI技術とその応用を専門家が紹介します。研究の効率化や新たな発見につながるAI活用の最前線を知る絶好の機会です。AIと植物バイオの未来を共に考えましょう。
山本康平(Finding AI)「ChatGPTと生成AIで広がる知的生産の新しいかたち」
久米慧嗣(Bio"Pack"athon)「生成AIの最新動向とバイオ分野への応用を探る」
池田秀也(DBCLS)「実験サンプルデータベースの混沌に大規模言語モデルで挑む」
爲重才覚(京都府立大学)「見るコストの削減によって見えてきた植物の野外環境応答 -機械学習の利用例-」
伊藤潔人(株式会社日立製作所)「代謝設計とAI技術:文献・公開データからの知識抽出による設計提案」
S3「エンジニアリングバイオロジーが拓くCO2資源産業への道」
Engineering Biology: Paving the Way to a CO2 Resource Industry
オーガナイザー:平井優美(理化学研究所)、水谷正治(神戸大学)
概要:微生物宿主による化成品生産はすでに実用化されているが、CO2を直接資源として利用できる点や、複雑な構造を持つ高付加価値化合物の生産が可能である点から、植物宿主への期待が高まっている。一方、CO2固定能の向上に関する研究開発は、これまで主に農業的な視点に基づいて行われてきた。本シンポジウムでは、CO2の固定と利活用を一体として捉え、多様な社会的・産業的ニーズに応える「CO2資源産業」の創出を目指した、エンジニアリングバイオロジーを基盤とした最新の取り組みを紹介する。
相澤康則(東京科学大学)「東京科学大学/GteXゲノム構築拠点での研究活動」
持田恵一(理化学研究所)「持続的な物質生産のための微細藻類を用いたCO2の固定と利用技術の開発」
三浦謙治(筑波大学)「植物一過的発現系「つくばシステム」を用いた有用物質生産」
関原明(理化学研究所)「キャッサバの活用によるカーボンニュートラルな循環型社会への貢献を目指して」
中村友輝(理化学研究所)「種子の油脂蓄積におけるプラスチドと小胞体の代謝的協調」
中山尚美(OIST)「合成生物学を用いた植物発生工学(トップダウンとボトムアップのアプローチ)」